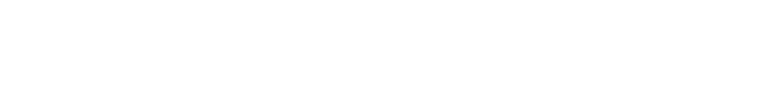
 北海道から九州の沿岸まで幅広く生息し,中海でもみられます。ヤドカリのなかでは小型で、右のはさみが左より大きいところが「ホンヤドカリ科」というグループの特徴です。ユビナガホンヤドカリの繁殖シーズンは冬から春のあいだです。オスは「はさみ」でメスの貝殻をつかむ「交尾前ガード」を行います。寒い季節の観察はたいへんですが、ぜひ一度見てみたいですね。
北海道から九州の沿岸まで幅広く生息し,中海でもみられます。ヤドカリのなかでは小型で、右のはさみが左より大きいところが「ホンヤドカリ科」というグループの特徴です。ユビナガホンヤドカリの繁殖シーズンは冬から春のあいだです。オスは「はさみ」でメスの貝殻をつかむ「交尾前ガード」を行います。寒い季節の観察はたいへんですが、ぜひ一度見てみたいですね。
 中国地方のみに生息するイワナのなかまで、夏の最高水温が20℃を超えない河川の上流域にくらしています。分布域や個体数の少なさから幻の魚と呼ばれています。名前の由来は、朝鮮半島で「魚」を意味する「コギ」という言葉が、半島から渡ってきた製鉄技術者によって伝えられ定着したという説があります。他のイワナと異なり、鼻先まで白い斑点があります。
中国地方のみに生息するイワナのなかまで、夏の最高水温が20℃を超えない河川の上流域にくらしています。分布域や個体数の少なさから幻の魚と呼ばれています。名前の由来は、朝鮮半島で「魚」を意味する「コギ」という言葉が、半島から渡ってきた製鉄技術者によって伝えられ定着したという説があります。他のイワナと異なり、鼻先まで白い斑点があります。
 体に黒い斑点が入り、胡椒の実をまいたような模様なので、コショウダイと呼ばれるようになったと言われています。幼魚と成魚で模様が変わり、幼魚の時は全身黒ですが、成長するにしたがって縞模様と黒い斑点模様が現れてきます。成魚は体長約60cmになります。食用としても人気があり、刺身や煮つけでおいしく食べることができます。
体に黒い斑点が入り、胡椒の実をまいたような模様なので、コショウダイと呼ばれるようになったと言われています。幼魚と成魚で模様が変わり、幼魚の時は全身黒ですが、成長するにしたがって縞模様と黒い斑点模様が現れてきます。成魚は体長約60cmになります。食用としても人気があり、刺身や煮つけでおいしく食べることができます。
 ネンブツダイはオスが口の中に卵をくわえて守るおもしろい習性を持っています。口の中の卵を世話する時、口をモゴモゴと動かす姿が念仏を唱えているように見えることから「念仏鯛」という名まえがつきました。 繁殖期になるとペアを作ることでも知られていて、水槽の中でも仲良く2匹並んで泳いでいる姿を見ることができます。
ネンブツダイはオスが口の中に卵をくわえて守るおもしろい習性を持っています。口の中の卵を世話する時、口をモゴモゴと動かす姿が念仏を唱えているように見えることから「念仏鯛」という名まえがつきました。 繁殖期になるとペアを作ることでも知られていて、水槽の中でも仲良く2匹並んで泳いでいる姿を見ることができます。
 全長7㎝に達し、日本でくらす水生昆虫のなかで最大です。カマのような太い前脚で魚やカエルなどを捕まえます。捕まえた生きものの体の中に針状の口で消化液を流し込み、少し溶けた肉を吸いとるように食べます。水深の浅い水域を好み、水草の多い池や水田などに生息しています。絶滅が心配されている生きものであり、ゴビウスではタガメの繁殖に取り組んでいます。
全長7㎝に達し、日本でくらす水生昆虫のなかで最大です。カマのような太い前脚で魚やカエルなどを捕まえます。捕まえた生きものの体の中に針状の口で消化液を流し込み、少し溶けた肉を吸いとるように食べます。水深の浅い水域を好み、水草の多い池や水田などに生息しています。絶滅が心配されている生きものであり、ゴビウスではタガメの繁殖に取り組んでいます。
 8本の口ひげを持つナマズのなかまです。胸びれと背びれに鋭い棘があり、刺されると大変痛みます。
8本の口ひげを持つナマズのなかまです。胸びれと背びれに鋭い棘があり、刺されると大変痛みます。 
コウホネは、漢字で「河骨」と書きます。根のように見える太い茎が骨のように見えたことからこの名前がついたそうです。物々しい名前のイメージとは裏腹に、つややかな緑色をした大きな葉を水面から立ち上がらせた美しい姿をしています。初夏に咲く黄色い花は野外でもひと際目立ち、まさに池の花形のような存在感があります。

汽水域の中海では、5月頃に見られるクラゲです。毒のある細長い触手を40~50本持ち、この触手でエサとなる小さな生きものやクラゲのなかまを捕らえます。毒は強く、刺されると激しく痛みます。 現在、ゴビウスで繁殖させたアカクラゲを展示してます。長い触手をなびかせて泳ぐ姿はたいへん見応えがあります。

島根県では高津川水系などのごく限られた河川に生息します。はじめてイシドジョウに気づいたのは、広島県の学校教員であったことが文献に残っており、その方は『ホホスジドジョウ』と呼び、地域の子どもたちに話をされていたようです。 石が多い場所を好むことから和名はイシドジョウと名づけられましたが、頬にある2本の模様にもご注目ください。
 全長約6cmで、宍道湖の湖岸や付近の水路等に生息しています。北陸地方の汽水域にも生息していますが、宍道湖で初めて発見されたため、この名まえが付けられました。また、3月~4月の産卵期を迎えると、メスの体には黒色と黄色の横じま模様の鮮やかな婚姻色があらわれます。春だけの貴重な姿です。
全長約6cmで、宍道湖の湖岸や付近の水路等に生息しています。北陸地方の汽水域にも生息していますが、宍道湖で初めて発見されたため、この名まえが付けられました。また、3月~4月の産卵期を迎えると、メスの体には黒色と黄色の横じま模様の鮮やかな婚姻色があらわれます。春だけの貴重な姿です。
 全長約20㎝。本州の日本海側に多く、島根県では河川の中流域、河口域に生息しています。降河回遊魚で、秋から冬に河口から沿岸域へ下り1~3月に産卵します。アユカケという名前は、えらぶたの縁に4本の棘があり、その棘でアユをひっかけて食べるという言い伝えに由来します。実際にはそのような行動はせず、エビや小魚を丸のみします。
全長約20㎝。本州の日本海側に多く、島根県では河川の中流域、河口域に生息しています。降河回遊魚で、秋から冬に河口から沿岸域へ下り1~3月に産卵します。アユカケという名前は、えらぶたの縁に4本の棘があり、その棘でアユをひっかけて食べるという言い伝えに由来します。実際にはそのような行動はせず、エビや小魚を丸のみします。
 中国の伝説に「コイが滝をのぼると龍になる」という話があります。縁起の良い魚として知られているこのコイを新年最初の今月の生きものに選んでみました。普段はのんびりと泳いでいますが、夕方になると水槽を上に下にと勢いよく泳ぎ回りはじめます。この時間になるとエサをもらえることがわかっているのかも知れません。同じように時間帯によって行動が変わる生きものがほかにもいますのでぜひ探してみてください。
中国の伝説に「コイが滝をのぼると龍になる」という話があります。縁起の良い魚として知られているこのコイを新年最初の今月の生きものに選んでみました。普段はのんびりと泳いでいますが、夕方になると水槽を上に下にと勢いよく泳ぎ回りはじめます。この時間になるとエサをもらえることがわかっているのかも知れません。同じように時間帯によって行動が変わる生きものがほかにもいますのでぜひ探してみてください。
 全長約15㎝で、北海道南部以南から西太平洋、オーストラリア南部の岩礁に生息しています。下顎の先端部分にある感覚溝には、発光バクテリアが共生しており、弱い光を出します。また、鮮やかな黄色の体色に黒で縁どられた鱗が特徴的で、硬く厚い鱗が、松かさに似ていることから、この名が付いたとされています。ぜひ、想像しながら観察してみてください。
全長約15㎝で、北海道南部以南から西太平洋、オーストラリア南部の岩礁に生息しています。下顎の先端部分にある感覚溝には、発光バクテリアが共生しており、弱い光を出します。また、鮮やかな黄色の体色に黒で縁どられた鱗が特徴的で、硬く厚い鱗が、松かさに似ていることから、この名が付いたとされています。ぜひ、想像しながら観察してみてください。
 日本全国に分布し、平野や田んぼに生息しています。ニホンアマガエルは身近な両生類でもあり、子どもたちからの人気も高いです。緑色のイメージが強いかもしれませんが、周囲の環境に合わせて体色を変化させることができます。
日本全国に分布し、平野や田んぼに生息しています。ニホンアマガエルは身近な両生類でもあり、子どもたちからの人気も高いです。緑色のイメージが強いかもしれませんが、周囲の環境に合わせて体色を変化させることができます。
 マゴチは、体が平たく、体色も砂に似た色をしています。砂地にひそみ、外敵やエサとなる生きものにも発見されにくくするためです。また、目も上向きについており、近くを泳ぐエサのエビや小魚を見つけやすくなっています。ところが、3番水槽にいるマゴチは、なぜか石の上にいることが多く、目はガラス越しにこちらをじっと見ているような気がします。
マゴチは、体が平たく、体色も砂に似た色をしています。砂地にひそみ、外敵やエサとなる生きものにも発見されにくくするためです。また、目も上向きについており、近くを泳ぐエサのエビや小魚を見つけやすくなっています。ところが、3番水槽にいるマゴチは、なぜか石の上にいることが多く、目はガラス越しにこちらをじっと見ているような気がします。
 体長約15センチで、主に中海に生息しています。宍道湖や中海では、「モロゲエビ」や「本庄エビ」とも呼ばれ、宍道湖七珍のひとつとしても有名なエビです。しかし、近年は数が減っており、市場では高値で取引されています。また、普段は砂の中に潜ってじっとしていますが、エサの赤虫を与えると、においをたよりに活発に泳ぎまわります。ぜひ、じっくり観察してみてください。
体長約15センチで、主に中海に生息しています。宍道湖や中海では、「モロゲエビ」や「本庄エビ」とも呼ばれ、宍道湖七珍のひとつとしても有名なエビです。しかし、近年は数が減っており、市場では高値で取引されています。また、普段は砂の中に潜ってじっとしていますが、エサの赤虫を与えると、においをたよりに活発に泳ぎまわります。ぜひ、じっくり観察してみてください。
 お盆の時期になると、海でクラゲを見ることが多くなります。その多くはミズクラゲという種で、傘の部分に白く透けた四つ葉のクローバーのような形があるのが特徴です。これはミズクラゲの胃と生殖腺です。まれに胃の数が、4つではなく、5つや6つのものもいます。海で見かけた際は、ミズクラゲの傘に注目してみてはいかがでしょうか。
お盆の時期になると、海でクラゲを見ることが多くなります。その多くはミズクラゲという種で、傘の部分に白く透けた四つ葉のクローバーのような形があるのが特徴です。これはミズクラゲの胃と生殖腺です。まれに胃の数が、4つではなく、5つや6つのものもいます。海で見かけた際は、ミズクラゲの傘に注目してみてはいかがでしょうか。
 中国大陸や朝鮮半島が原産の外来種であるカムルチーは、最大で80㎝ほどにもなる大型の肉食魚です。日本ではタイワンドジョウと共に総称で「雷魚」とも呼ばれており、海外では顔つきがヘビに似ていることから、スネークヘッドなどと呼ばれています。 名前や見た目から怖いイメージもあるかもしれませんが、ぜひ実物を見に来てください。
中国大陸や朝鮮半島が原産の外来種であるカムルチーは、最大で80㎝ほどにもなる大型の肉食魚です。日本ではタイワンドジョウと共に総称で「雷魚」とも呼ばれており、海外では顔つきがヘビに似ていることから、スネークヘッドなどと呼ばれています。 名前や見た目から怖いイメージもあるかもしれませんが、ぜひ実物を見に来てください。
 全長4~7cmで、本州、四国、九州の河川や渓流周辺に生息します。4月から7月の繁殖期を迎えると、岩の下などに潜って産卵します。また、成熟したオスは、鹿に似た声で鳴くことから、「河鹿蛙」とも呼ばれます。ゴビウスでは、夕方になると鳴き声を耳にすることがあります。
全長4~7cmで、本州、四国、九州の河川や渓流周辺に生息します。4月から7月の繁殖期を迎えると、岩の下などに潜って産卵します。また、成熟したオスは、鹿に似た声で鳴くことから、「河鹿蛙」とも呼ばれます。ゴビウスでは、夕方になると鳴き声を耳にすることがあります。
 5月5日は「こどもの日」。今回はゴビウス生まれの「ニホンイトヨ」を紹介します!「ニホンイトヨ」は島根県レッドデータブックに絶滅危惧種と選定され、かつては宍道湖や中海で見ることができましたが、近年はその姿をほとんど見ることができません。ゴビウスでは、館内で繁殖させ、生まれた個体を展示しています。この機会に貴重な姿を見てみてはいかがでしょうか。
5月5日は「こどもの日」。今回はゴビウス生まれの「ニホンイトヨ」を紹介します!「ニホンイトヨ」は島根県レッドデータブックに絶滅危惧種と選定され、かつては宍道湖や中海で見ることができましたが、近年はその姿をほとんど見ることができません。ゴビウスでは、館内で繁殖させ、生まれた個体を展示しています。この機会に貴重な姿を見てみてはいかがでしょうか。
 去年8月ごろから展示を始めたスミウキゴリは、当初は3センチほどの大きさでしたが、今では大きく成長し、はっきりとした婚姻色も確認できるようになりました。普段、水槽低層でホバリングしながらフワフワと泳いでいます。急に水槽に近づくと驚いて物陰に隠れてしまうので、観察する際は、水槽にゆっくりと近づくと良いですよ。
去年8月ごろから展示を始めたスミウキゴリは、当初は3センチほどの大きさでしたが、今では大きく成長し、はっきりとした婚姻色も確認できるようになりました。普段、水槽低層でホバリングしながらフワフワと泳いでいます。急に水槽に近づくと驚いて物陰に隠れてしまうので、観察する際は、水槽にゆっくりと近づくと良いですよ。
※今月の生きものバックナンバーです。現在は水槽No.が変更になっていたり展示を終了している場合があります。予めご了承ください。